[PR]
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
自動操舵の国際基準を策定する国連の専門家会議、東京で開催…4月19日から21日
リスト取りシステムの詳しいノウハウこちら
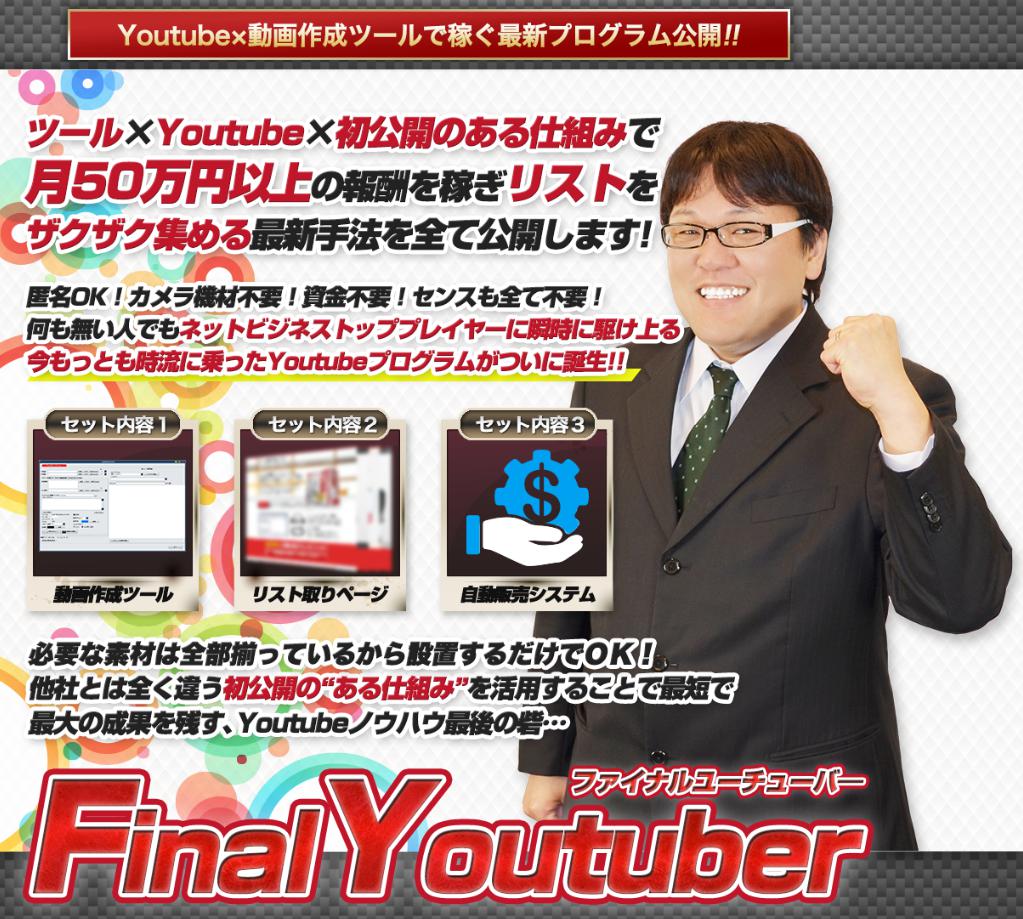
自動操舵の国際基準策定に関する第6回国連専門家会議が4月19~21日にかけて東京で開催される。
[関連写真]
自動車の自動運転技術は、交通事故の大幅な削減、高齢者の移動支援など、様々な効果が期待されている。このため、国内を含む世界の自動車メーカーや部品メーカーが、開発・実用化に取り組んでいる。
自動運転技術のうち、衝突被害軽減ブレーキなどの進行方向の自動制御は、多くの技術が実用化されている一方で、自動追い越しなど、自動でハンドルを操作する「自動操舵技術」も現在、世界各国で技術開発が進められている。
こうした状況を踏まえ、昨年4月、自動車の国際基準を策定する「国連の自動車基準調和世界フォーラム」(WP29)の傘下に「自動操舵専門家会議」が設置され、国際基準策定の議論を開始した。日本はドイツとともに専門家会議の共同議長を務め、議論を主導している。
今回6回目となる会合が東京で開催される。日本、ドイツ、英国、欧州委員会(EC)、スウェーデン、デンマーク、韓国、オランダ、フランスなど各国政府、OICA(国際自動車工業連合会)、CLEPA(欧州部品工業会)など、産業界から出席者が訪れる予定。
今回は、目的に応じた自動操舵技術の分類と自動操舵技術の認証のための試験法などを議論する予定だ。専門家会議の内容は、自動車メーカーの技術開発に係る事項も含むことから非公開となっている。
《レスポンス レスポンス編集部》
ポリス・ランナーで駆け抜ける交通安全運動出動式...警視庁戸塚署
奇跡の現金化システムの詳しいノウハウこちら

春の交通安全運動初日となる6日、警視庁戸塚署が警察官ランナーを組織して、出動式を駆け抜けた。被害者になりやすい子どもや高齢者に、より接近して語りかけようという警視庁初の試みだ。
[関連写真]
戸塚署の男性警察官12人、女性警察官8人の20人で結成された。その名も「戸塚TSR(=Traffic Safty Runner)、交通安全走者だ。いつもは制服の警察官がランニングウエアに着替え、担当する地域を走って巡回。すれ違う歩行者1人ひとりに交通ルールの順守を呼びかける。
「パトカーや白バイからでは一方通行の呼びかけしかできない。ランナーとなって歩行者目線に立つことで、相互交流の交通安全をしたい」(同課交通総務担当)
戸塚TSRの一群は、出動式後にそのまま新宿区西早稲田の明治通り馬場口交差点まで走った。高齢者やベビーカーを押す親子連れに事故防止を訴えた。直接、高齢者の靴に反射シールを貼り付けて、車両から認識されやすい反射材の活用を示したりもした。
さらに、戸塚TSRは車両の侵入が難しい商店街や生活道路を走ることで「交通問題点の把握」(前同)という別の役割も帯びて、交通事故防止の新たな貢献を期待されている。
春の交通安全運動は16日まで、全国で展開される。
《レスポンス 中島みなみ》
警視庁白バイ安全運転競技大会、バイク104台、選手90人が参加で盛大に
リストが取れる!稼げた!ツール&詳しいノウハウこちら
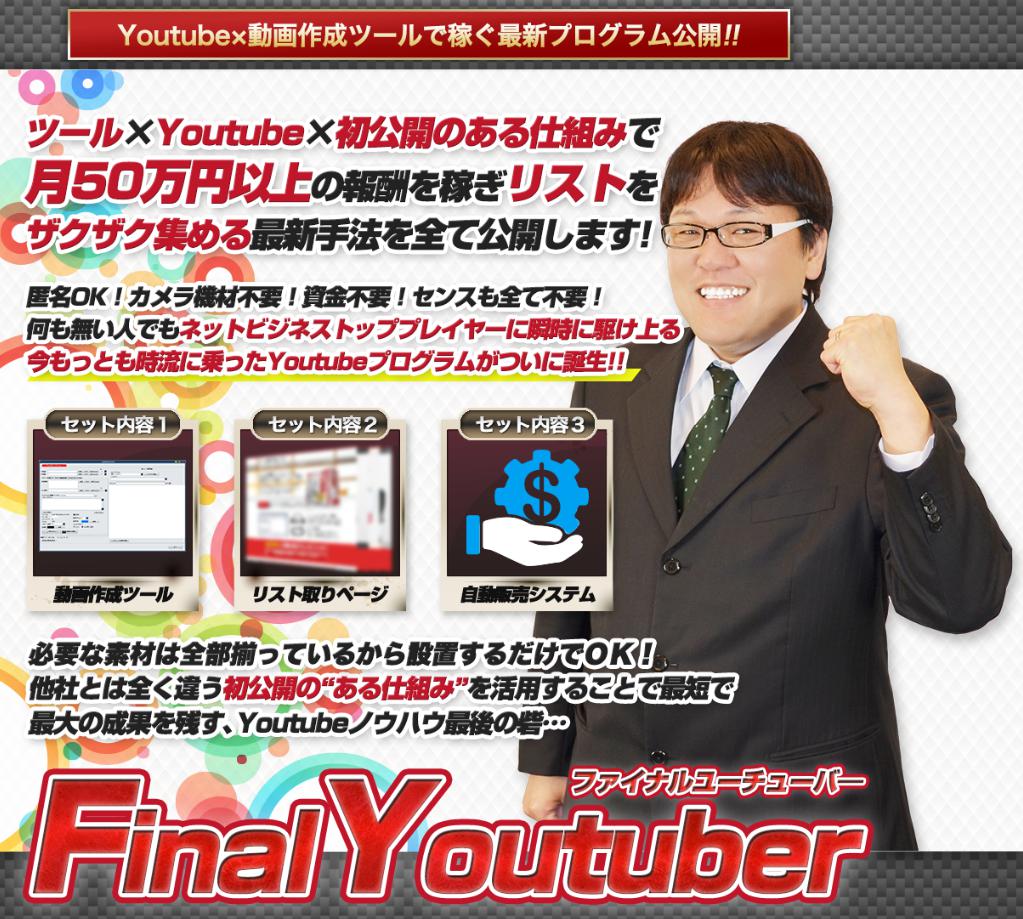
白バイ乗務員の運転技能の向上などを目的に開催される警視庁の「白バイ安全運転競技大会」が、今年も世田谷区喜多見の交通安全教育センターで開催された。
[関連写真]
今年は警視庁10方面の交通機動隊、高速道路交通機動隊、各署の白バイ乗務員90人が参加。白バイ104台が参加した。3人1組のチームを作り、運転技術を競った。午前中にバランス走行、午後にスラローム走行を実施。ただ、前日からの午前中の路面はウエット。車両コントロールに苦しむ大会となった。
大会会長の大沢裕之交通部長は「事故対策を推進するにあたって、機動力を有する白バイが不可欠であり、極めて重要であることを認識し、日々の訓練を怠らず、都民の期待に応えていただきたい。大会は白バイ乗務員が一堂に会し、連帯感を深める絶好の機会。所属を代表して出場する選手には、日ごろの成果をいかんなく発揮されたい」と、訓示。
昨年の優勝チームである第九方面交通機動隊から矢津顕司巡査長が選手として「白バイ乗務員個々の安全運転技能の向上を図り 重大交通事故の防止を図り、東京の安全安心を守ることを誓います」と、宣誓した。
また競技会場とは別に見学者のためのイベント会場では、災害時に情報収集にあたるオフロード白バイセロー250や儀礼用のサイドカー付きゴールドウイング、交機隊と高速隊に配備されることになったフェアレディZ NISMOなどが展示され、親子が記念写真を撮影するなどの姿がみられた。
競技の合間には、交通パトカーの競技走行も行われた。また、テレビ局記者などが競技の一部を体験。運転技術の難しさを見学者に伝えた。
《レスポンス 中島みなみ》
「一歩間違えば大惨事」メトロ乳母車事故 新米車掌が「非常停止をためらった」ワケ
リストが取れる!稼げた!ツール&詳しいノウハウこちら
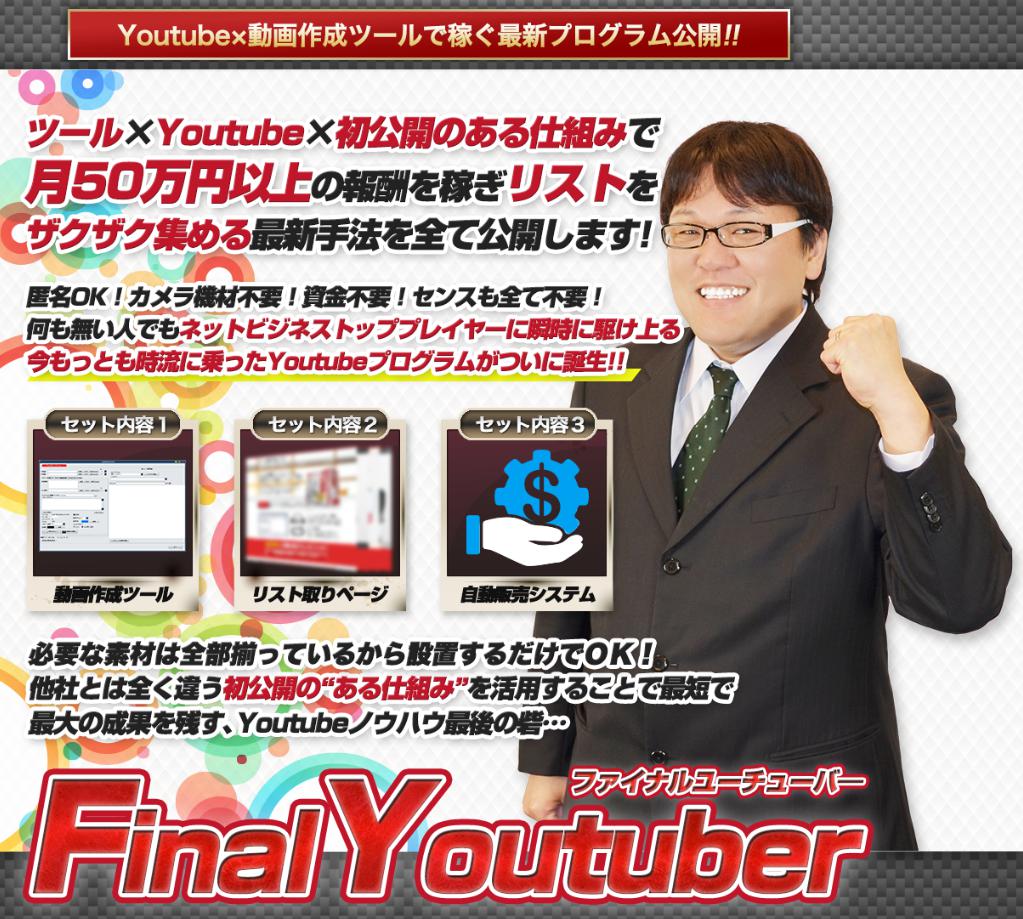
東京メトロの半蔵門線で、ドアにベビーカーがはさまったまま電車を出発させ、100メートルほど引きずって線路に落下させる事故があった。2度にわたって非常通報ボタンが押されたが、車掌は非常ベルには気付きながら電車を停止させず、ベビーカーはドアにはさまったまま引きずられた。しかも車掌は、その約15分後に乗務から外されて上司から指摘されるまで、ベビーカーがはさまっていたことを把握していなかった。
【写真】ドアが開いていると赤いランプが点灯する
ベビーカーに赤ちゃんは座っていなかったため、けが人はいなかったが、石井啓一国交相は「一歩間違えれば大事故につながりかねない事案」だとして原因究明と再発防止策の策定を指示した。
■車内とホームで非常停止ボタンが押される
事故は2016年4月4日15時1分ごろ、半蔵門線の九段下駅で起きた。中央林間発押上行き(10両編成)の6両目付近から母親と子どもが電車に乗り込み、その直後に父親がベビーカーを押しながら乗ろうとしたところ、ドアが閉まって前輪のパイプが挟まった。電車はそのまま動き出し、ベビーカーはそのまま約100メートルにわたって前方に引きずられてホームの端にある柵に激突。この衝撃でベビーカーはドアから外れ、落ちて壊れた。
通常、ドアが開いているときにはドア上部の赤いランプがつき、車掌はランプが消えたことでドアが正しく閉まったことを確認する。大きさが1.5センチ以上のものが挟まった場合はランプが消えないため、車掌はドアが正しく閉まっていないことに気付くことができる。だが、今回はさまったベビーカーの部品は1.5センチより小さかったためランプが消え、車掌は異常に気付かなかった。
車掌は10両目の最後尾に乗務しており、モニターや目視でホームに異常がないか確認した上で運転手に出発の合図を送る。東京メトロ広報部によると、ベビーカーがあった6両目付近は、最後尾から目視で確認すべき範囲だ。だが、車掌はベビーカーの存在に気付かずに出発の合図を出してしまった。
電車が動き出してからも判断ミスがあった。電車が100メートルほど走った時点で車内にいた母親が非常通報ボタンを押し、さらに50メートル走ってからホームにいた人も非常停止ボタンを押した。それにもかかわらず、電車は通常の速度で走り続けた。車掌は2回にわたって電車を止めるチャンスを逃していたことになる。
SIP-adus、自動運転システムの新しい責任者に葛巻清吾PD
リストが取れる!稼げた!ツール&ノウハウこちら
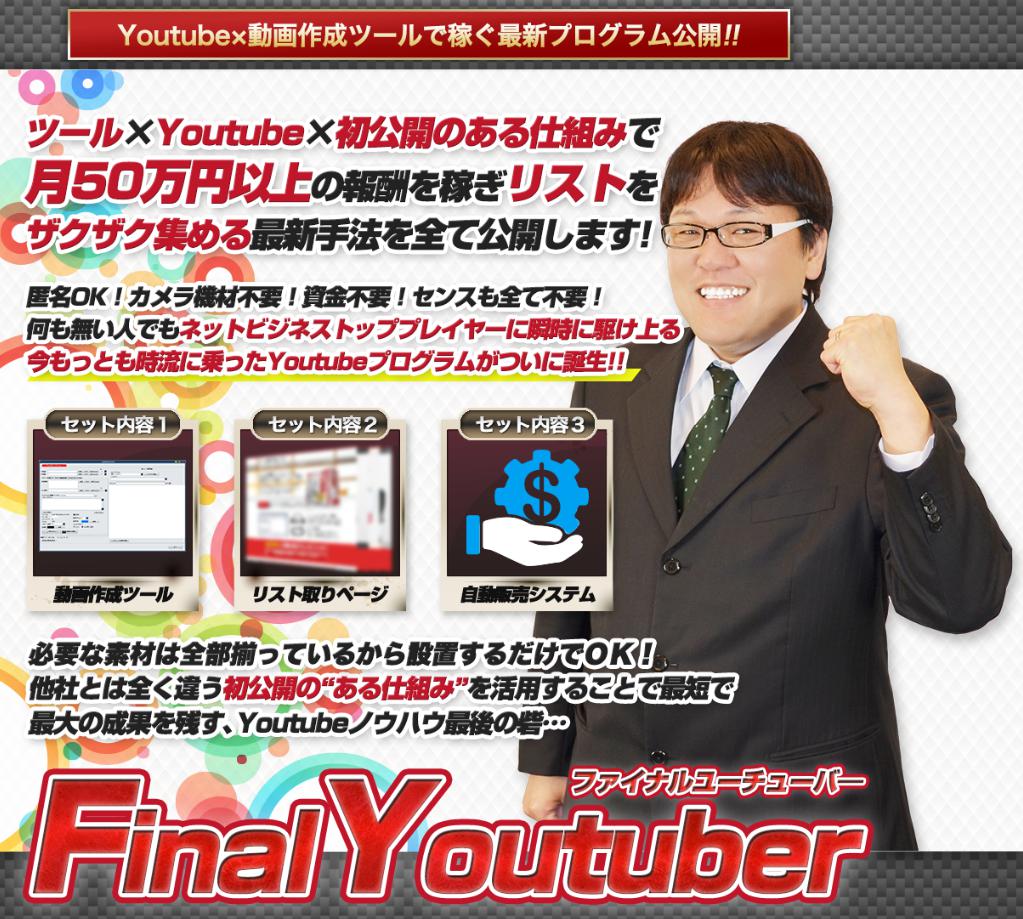
科学技術の変革を実現するために政府が最重要と位置付ける「戦略的イノベーション創造プログラム」の1つである「自動走行システム」(SIP-adus)の責任者として葛巻清吾氏がプログラムディレクター(PD)に4月1日付で選任された。
SIP-adusは自動走行をテーマとして、自動車メーカーや関係する国土交通省、経済産業省、総務省、警察庁、内閣府など関係省庁が参加。基礎研究から実用に至る研究開発を官民一体で推進する取り組み。葛巻氏が就任したPDは、これら参加メンバーを政府参与という立場で横断的に主導していく役職。プログラムの中心的役割を果たす。任期2年。
14年のSIP-adus発足時、葛巻氏はサブプログラムディレクター(サブPD)として、PDの故・渡邉浩之氏(ITSジャパン会長/元トヨタ自動車専務)を支えた。渡邉氏が入院中は代行としてSIP-adusをけん引した。自動走行についての共に講演に立ったこともあった。
今回の就任は、渡邊前PDの死去に伴う後任ではなく、任期終了による新たな選考によるもの。議長の安倍晋三首相が議長を務める総合科学イノベーション会議で決定した。
《レスポンス 中島みなみ》
カレンダー
リンク
カテゴリー
フリーエリア
最新コメント
最新記事
プロフィール
ブログ内検索
アーカイブ
最古記事
P R
